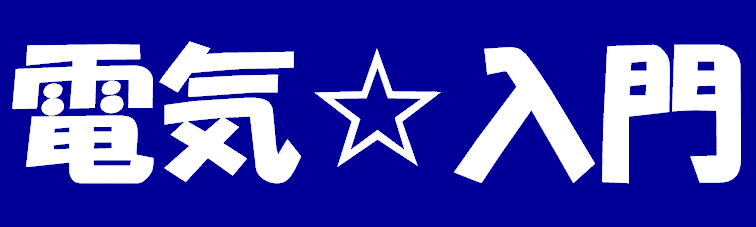技術士2次試験対策(口頭試験)①
口頭試験受験の心構え
資格試験で口頭試験を実施するものはあまり多くありませんので、口頭試験に慣れている方は少ないと思います。まず口頭試験の流れを説明します。
技術的体験論文の提出
筆記試験に合格したら、技術的体験論文を提出します。論文の位置付けは
「口頭試験においては、技術的体験論文は口頭試験の一部として使用し、その内容を踏まえた上で、口頭試験の採点を行うこととする。」
とされています。簡単に言えばプレゼン資料になります。口頭試験で試験官が手元に置いていることを意識して、分かりやすい論文になるよう心がけましょう。
口頭試験当日
受験票に記載された時刻に間に合うよう試験会場に行き、受付を済ませます。受付後、受験者が試験時刻まで待機する控室が用意されていますが、外出しても大丈夫です。試験時刻の15分前になったら試験室の前の廊下に置かれた椅子に移動します。このあたりは受付時に説明されます。
前の受験者が口頭試験を終えて退室してきます。そこから採点を行い、試験時刻になると室内から試験官が呼びに来ます。
試験室には、他の試験官が待っています。入室したら、一礼し「失礼します。」挨拶します。
予備に来た試験官から、荷物を置く場所を指示されます。椅子か台がありますので、カバン等はそこにおきます。
この時点ではまだ着席しません。受付時に試験室に入ったら受験番号と氏名を言うように指示されます。試験官から「受験番号とお名前をお願いします。」と言われたら、「○○○の□□と申します。よろしくお願い致します。」と言います。
試験官から着席を促されたら、「失礼します。」と言って着席します。
ここから試験は始まります。
試験官は2名以上で、論文に関する質問や技術的な質問をする試験官と、技術士法や倫理の質問をする試験官がいます。
口頭試験の流れは、
①経歴の説明
②論文の説明
③試験官から論文に関する質問
④専門とする分野に関する質問
⑤技術士法や倫理に関する質問
といった感じです。
一通り質問が終わると終了となります。制限時間いっぱいまで行う場合と多少早く終わる場合があります。カバン等の荷物を持って「ありがとうございました。」と挨拶し退室します。
口頭試験の質問に対する回答の仕方
口頭試験では下記の点に気をつけます。
①質問をよく聞いて、的を得た回答をします。「はい」か「いいえ」で答える質問に対し、理由から説明すると、理解しにくいやりとりになりがちで、ストレスを感じさせてしまいます。
「○○を行ったのですか?」
「はい。理由は○○です。」
というやりとりが円滑に試験を進めるコツです。
②わからないことを質問されたら「すみません。分かりません。帰ったら調べてみます。」と答えます。すると代わりの質問をしてくれます。分からない質問に対して悪あがきをするのは禁物です。知っていることを言って煙に巻くということは通用しないですし、限られた試験時間を浪費してしまいます。1つ2つ答えられない質問があっても、十分挽回できます。
③試験官と意見が食い違ったり、自分の回答を否定されても引き下がることが大事です。間違っても討論にならないようにします。「私は○○と理解していましたが、間違っているかも知れませんので、調べてみます。」のように、心証を害しないように収めましょう
TOPページに戻る
サイト内検索
電気とはなにか
電気の歴史
電荷
電気力線と電束
原子と分子と電子
電気の回路と水の回路
電流とは
電圧とは
抵抗とは
電力と電力量
直列・並列接続の合成抵抗
分圧と分流
直流と交流
正弦波交流
抵抗・リアクタンス・インピーダンス
電界と磁界
磁荷
磁力線と磁束
磁気ヒステリシス
コイルとインダクタンス
コンデンサと静電容量
共振
力率と皮相・有効・無効電力
零相電流とI0r・I0c
3相交流
ベクトル図の使い方
電線にとまった鳥が感電しない理由
需要率と負荷率と不等率
パーセントインピーダンス法(%Z)
ホイートストンブリッジ
スターデルタ変換・デルタスター変換
電圧降下
過渡現象
過渡現象(R-L直列回路)
過渡現象(R-C直列回路)
原子力発電の仕組み
水力発電の仕組み
火力発電の仕組み
太陽光発電の仕組み
関東と関西で周波数が違う理由
なぜ交流送電なの?
停電
瞬時電圧低下
受電方式
スポットネットワーク受電方式の仕組み
ループ受電方式の仕組み
進相コンデンサと力率割引
遮断器と開閉器と断路器
開閉サージ
GIS(ガス絶縁開閉装置)
UGS・UAS・PGS・PAS
保護継電器
変圧器(トランス)
励磁突入電流
接地(アース)
統合接地
接地用補償コンデンサ
電源冗長化
フェランチ効果
オームの法則
クーロンの法則
キルヒホッフの法則
ファラデーの法則・レンツの法則
フレミングの法則
ミルマンの定理
テブナンの定理
ガウスの定理
重ね合わせの理
アンペア周回積分の法則
ビオ・サバールの法則
第3種電気主任技術者 理論
第3種電気主任技術者 電力
第3種電気主任技術者 機械
第3種電気主任技術者 法規
第2種電気主任技術者 1次理論
第1種電気主任技術者 1次理論
第1種電気主任技術者 1次電力
第1種電気主任技術者 1次機械
第1種電気主任技術者 1次法規
第1種電気主任技術者2次試験 電力・管理
第1種電気主任技術者2次試験 機械・制御
エネルギー管理士(電気) 電気の基礎
技術士一次試験 共通科目数学
技術士一次試験 共通科目物理
技術士一次試験 共通科目化学
技術士一次試験 基礎科目
技術士一次試験 電気電子部門 専門科目
技術士一次試験 適性科目
技術士二次筆記試験 電気電子部門 必須科目
技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 発送配変電
技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 電気応用
技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 電子応用
技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 情報通信
技術士二次筆記試験 電気電子部門 選択科目 電気設備
技術士二次筆記試験 総合技術監理部門 必須課目